今回はファクトフルネスを読んで理解したことを自分なりに解説をしていきたいと思います。この本は最近読んだ本の中でダントツでオススメの一冊です。
この本で得られる3つの視点
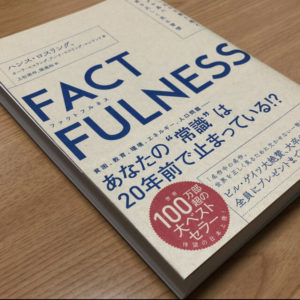
この本を理解することで、世界の見え方が3つの視点から変わります。
- 世界の見え方が変わるから
- 楽観的に生きるヒントが得れる
- 自分の決断の仕方が変わる
まずは、この本であった有名な正答率10%以下の難問を二つ紹介します。
低所得国に暮らす女子の何割が初等教育を修了するでしょうか。
A:20%
B:40%
C:60%
この二つの問題に対しての答えは「C」となり、低所得国の人口は実際は世界の9%しかいないということになります。
この本では、2つの問いに対して、多くの専門家を含めた人たちが両方の質問に対して「A」選択したというのが注目されています。
しかし、実際の答えは、そのような国の女の子の60%以上は初等教育を修了しているというデータがあるようです。
実際にデータを見ると過去20年の人口における貧困層の割合について調べると、20年前と比べ現代の貧困層の割合は半分にまで減ってることがわかります。
つまり、この20年は貧困層が最も早いスピードで減った期間ということ、そして、このように我々が持っている常識や思い込みは間違ってることが多いものです。
それは、世界情勢など大きなスケールだけではなく日々の生活でも全く同じことです。
逆に言うと、その無駄な思い込みをデータに囚われなければ、科学を使って正しい判断や決断ができる可能性が高くなるいうことではないでしょうか。
判断を狂わせる3つの思い込み

そして、この本で紹介されている決断や判断を狂わせる思い込みというのは、以下の三つ厳選して解説していこうと思います
- 恐怖本能
- 分断本能
- ネガティブ本能
恐怖本能
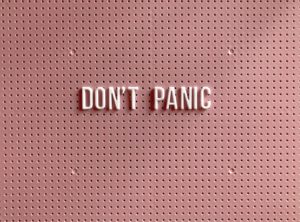
まず一つ目が恐怖本能です。
これは確率的にはあまり危険でないことを恐ろしいと考えてしまう思い込みです。
例えば、アメリカ人の51%は日常的にテロに対して恐怖を感じていると言われています。
過去に起きた911や銃の乱射事件が、起きたことを考えると当然だと思います。
しかし、実際テロはどれほど怖がるべきものなのでしょうか。
アメリカでのテロの死者は、1年平均159人対して飲酒が原因による死者は1年平均で69,000人です。
もし仮に、飲酒が原因で他人を殺した場合として仮定しても1年平均で7,502人となります。
つまり、テロで殺される確率より、酔っ払いに殺されるリスクの方が50倍も高いということになります。
しかも、2016年の死者のうちテロで亡くなったのは0.05%で、データ上で見ると亡くなった人の60%以上を死亡させた生活習慣病の方が恐ろしいと考えられます。
当然、これはテロなんて心配するなという意味ではありませんが、発生する確率が低いものに対して、強い思い込みのせいで必要以上に過剰に怯えてしまうと本当に危険で対策が必要なものが見えなくなってしまいます。
そして、これはテロなどの出来事だけではなく日常的な恐怖でも同じことです。
例えば人前で話すのが怖い人の中には人前で話して笑われるといった結果が怖いのではなく、人前で話すことが怖いものだと思い込んでるから怖くなってしまうという場合が少なくないものです。
だからこそ、現実的なリスクがあるから怖いのか、それとも強い思い込みから怖いのか、この区別をつけることで決断や判断の質を大幅に向上させることができます。
決断の際は、恐怖本能に惑わされていないか冷静に考えてみてください。
分断本能

次に、判断や決断を狂わせる二つ目の思い込みは焦り本能です。
これは、今、決めないと後悔してしまうんじゃないか、もしくは失敗してしまうんじゃないかという思い込みです。
これは、心当たりがある人も多いと思います。
例えば、不動産に部屋の内見をさせてもらうと「この部屋は人気なのでなるべく早く申し込まないとすぐに取られてしまいます」と必ず言っていい程に言われます。
他にも、本日限定の特別大セールという文字のせいで、いらないものを買ってしまったり、人間という生き物は、今決めないと損してしまうという恐怖に流されやすい生き物です。
その結果データや根拠を抜きにして、とりあえず決断を下そうとしてしまいます。
従って、決断をする際は「自分は今すぐ決めないといけない」というプレッシャーでこの決断をしているのか、それとも正確なデータや根拠に基づいて、決断を下そうとしているのかを見極めることが非常に重要です。
ネガティブ本能

そして、最後に紹介する判断を狂わせる思い込みはネガティブ本能です。
このネガティブ本能は、人が生まれ持った修正に加え、メディアの報道の偏りが大きな原因になっています。
これは当然のことで、ニュースに取り上げられるものは、ネガティブなものがほとんどで、簡単に言うと飛行機が墜落したというニュースが大きく報じられても、成田発のJAL便が、無事にロサンゼルスに着陸したという話はニュースにならないわけです。
だからこそ、我々が常日頃、触れている情報はネガティブなものに偏っていると知ることがとても重要になります。
他にも世界では10億人も安全な水を飲むことが出来ていないというニュースはあっても、1980年には人口の58%しか安全な水が飲めなかったけど、今では世界の88%が安全な水を飲めるようになったことは、なかなか言えないわけです。
同じように核弾頭の数が15,000発もあって、世界の平和は脅かされていると報道され煽られることはあっても、1980年代に64,000発あった核弾頭が、今では、15,000発まで減ったことは報道されないです。
もちろん、現在の問題に目を向けることは大事ですが、過去と現代を比べて進歩している点や良くなっている点も同じように評価しなければ、世界は悪くなる一方の理不尽なものと悲観的に捉えるしかなくなってしまいます。
そのため、データをもとにこの点は、過去と比較して進歩したけど、この部分はもっと改善しないといけないというように、ポジティブに行動できることがベストだと思います。
まとめと感想
この本を読んでみて感じたことは、偏見や思い込みにとらわれないためには、データで物事を正直に見ることが大切で、事実を直視することが大切だということ。
この本の目的は、データを見ることで私たちをバイアスから解き放ち、世界を正しく認識できるようにすることです。
また事実を知ることで、根拠のない不安を消し去り、人類や国や会社の課題に対しても正しく対処ができるようになります。
これらのことから、学校の知識なんかでも、古くて使えなくなったらそのまま使うのは危険でアップデートしていく意識はとても重要だと思いました。
つまり、生涯にわたって勉強してアップデートをすることが、これらの間違いに囚われないために大切だと言えるでしょう。
この本では、思考を狂わせる思い込みについて、他にも7つの視点で著書の中では紹介されています。
今回は、ほんの一部しか説明できていませんが、面白い本なので是非、買って読んでみても良いと思います。
今後も少しでも役に立つような情報を発信していこうと思っています。
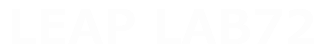
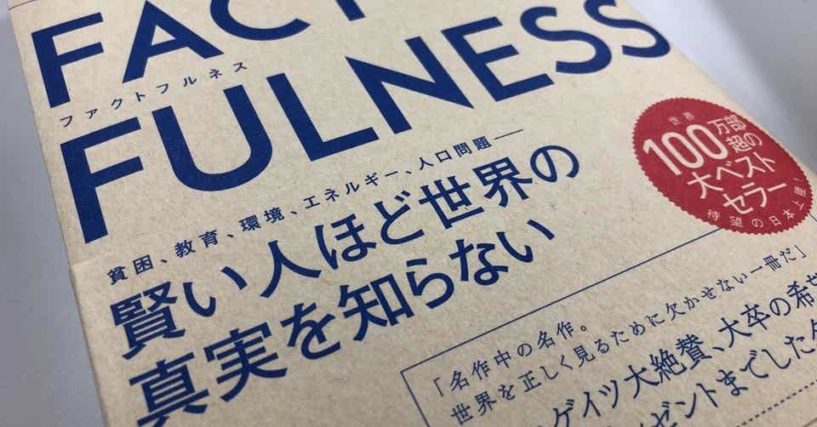


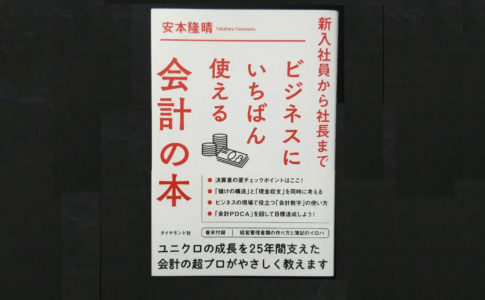

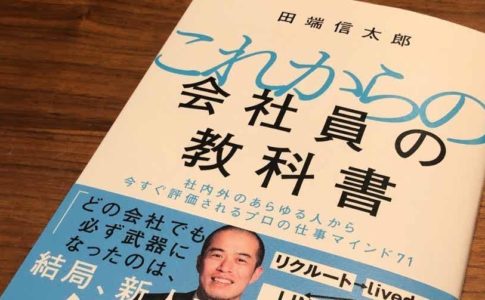
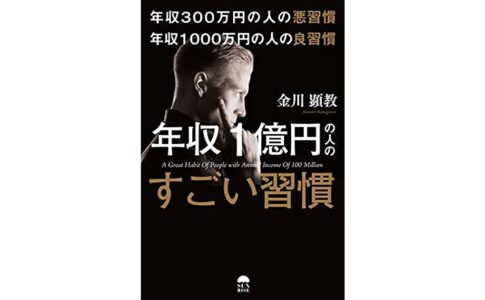
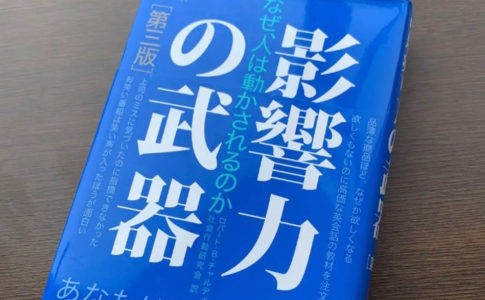
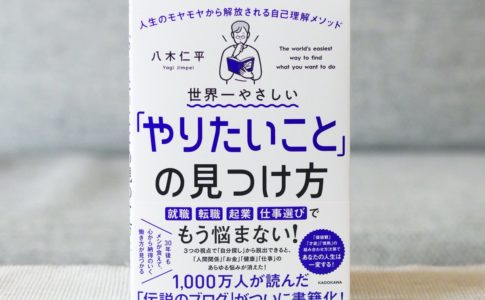
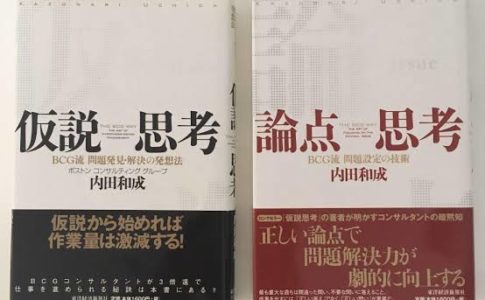
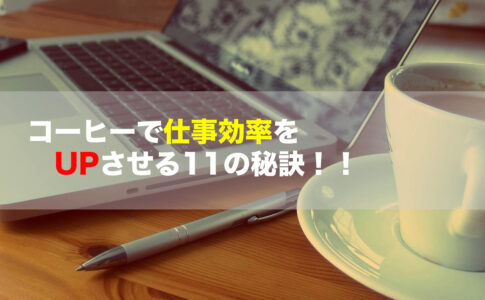




世界の人口の何パーセントが低所得国に住んでると思いますか。
※低所得とは1日の平均収入が2ドル以下の人を指します。
A:59%
B:32%
C:9%